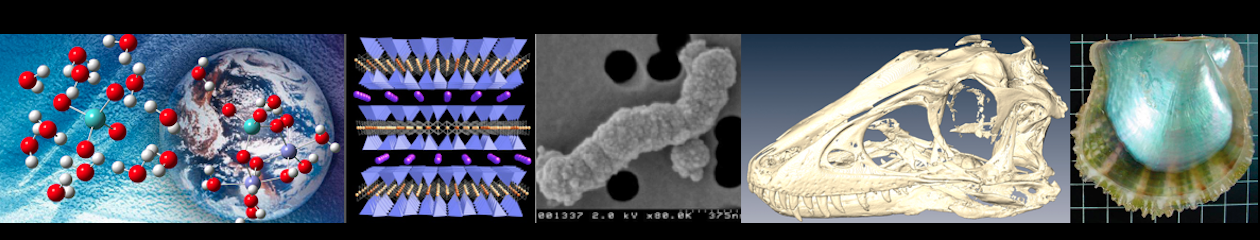日時:2021年10月25日(月) 18:00~19:00(発表45分,質疑15分)
講演者:鍵裕之 教授
演題:高圧下でアミノ酸をつなげる
要旨:
高圧下では有機化合物は重合反応や脱水縮合反応を起こす。我々がこれまで研究してきた有機化合物の圧力誘起反応をレビューしたのち、アミノ酸の圧力誘起反応について紹介する。前生物学的条件でアミノ酸からペプチドを生成させる研究がこれまで行われてきたが、我々は氷天体内部の高圧条件を想定し、室温条件でアミノ酸にGPaオーダーの圧力をかけ、脱水縮合反応が起こりペプチドが生成することを見いだした。セミナーではアミノ酸の凍結濃縮、ペプチドの不斉増幅の可能性についても述べる予定である。
●地球生命圏科学講座 修士中間報告会
●日時:2021年9月21日(火)
●プログラム(発表:18分,質疑:7分)
9:00 石水浩喜 板井研
9:25 宇野友里花 平沢研
9:50 海老澤俊 小暮研
10:15 加藤凜太郎 後藤研
10分休憩(10:40〜10:50)
10:50 河合敬宏 高橋研
11:15 菊地柾斗 遠藤研(對比地研)
11:40 後藤大貴 白井研
55分休憩(12:05〜13:00)
13:00 小長谷莉未 高橋研
13:25 竹田早英桂 板井研
13:50 田中風羽 佐々木研
14:15 西村大樹 鈴木研
14:40 沼倫加 平田研
15分休憩(15:05〜15:20)
15:20 東秀星 後藤研
15:45 村田彬 狩野研
16:10 森悠一郎 鍵研
16:35 吉田晶 鈴木研
17:00終了
●地球生命圏科学講座 博士2,3年 中間報告会
●日時:2021年6月21日(月)
●プログラム
D2(8名)
9:00–9:30 石川 弘樹
9:30–10:00 川島 彰悟
10:00–10:30 佐藤 英明
15分休憩
10:45–11:15 髙橋 玄
11:15–11:45 中野 晋作
11:45–12:15 名取 幸花
45分昼食
13:00–13:30 山口 瑛子
13:30–14:00 脇水 徳之
20分休憩
D3(3名)
14:20–15:10 上田 裕尋
10分休憩
15:10–16:00 佐久間 杏樹
10分休憩
16:10–17:00 鈴木 七海
日時:2021年5月24日(月) 18:00~
講演者:佐々木猛智 准教授
演題:博物館における生物多様性と進化の研究
要旨:
生物多様性は博物館が重要な拠点となる研究テーマのひとつである。多様性には、形態的多様性、生態的多様性、遺伝的多様性、化石記録の多様性など、様々な視点からの見方があり、時間軸が加わると進化の研究に結びつく。生物は種数が多い上に(貝類の現生種だけで20万種存在すると言われている)、個体変異があり、時間の経過とともに変化し、進化する。このような多様な研究対象に対して何らかの法則性を求める場合には、多くの分類群を調べる必要があり、網羅性(タクソンサンプリング)が重要になる。十分な量の生物試料を短期間で収集することは困難なことが多く、そのような場合には博物館標本が重要になる。近年の生物多様性の研究の例を紹介し、標本の重要性、電子化の重要性、そして今後の生物多様性研究の課題について解説する。
—– 2021年度 GBSセミナー予定 —–
第1回 4/26(月) 板井
第2回 5/24(月) 佐々木
第3回 6/21(月) 博士中間発表
第4回 9/21(火) 修士中間発表
第5回 10/25(月) 鍵
日時:2021年4月26日(月) 17:30~
場所:理学部1号館336号室+オンライン
演題:生態系地球化学 ~地球システム学とオミクスの間~
講演者:板井啓明 准教授
要旨:
「気候変動に代表される地球表層システムの摂動に伴い、高次生物に含有される特定元素濃度はどのように変化するか?」という問いを立てた時、答えるべきはどの分野の学者だろうか。生態学者は有力候補だが、私は系を問わずに元素の挙動を追跡する地球化学者が適任だと考える。C, H, N, S, O, Pなどの主要生元素を除けば、この問題を扱う国内地球化学者は多くはないので、私はこれに取り組もうと考えている。この知的体系を組み上げるには、環境・低次生態系・高次生態系を通貫する展望が必要である。各段階における技術的課題と、我々の取り組みについて紹介したい。
(1) 水圏高次生物への微量元素の生物濃縮性評価法
魚類や海棲哺乳類など、水圏食物網の上位に位置する生物の組織中元素濃度変動は、寿命の長さや、餌生物・回遊履歴の多様性から、考慮すべき要因が多い。一方、恒常性の高い元素は、環境や生態系構造の変化に依らず一定の濃度範囲に収まるであろう。これら要因についての基礎知見を得るための研究として、(i)海洋生物の食物網を介した微量元素移行、(ii)カツオ筋肉中微量元素濃度の地域差とその要因、(iii)カツオ筋肉中イオウ形態の海域間比較、(iv)海洋生物における鉄安定同位体比分布の特徴、(v)天然魚類の水銀濃縮へのバイオロギングデータの応用、(vi)水銀の大気海洋物理モデルと広域生物モニタリングデータのカップリング、の概要を紹介する。
(2) 水圏低次生態系における元素サイクル解析法の課題
低次生態系は、実験的研究と観測的研究の融合が発展させやすい対象だが、さしあたり取り組んでいるのは、10-1000 μmのサイズを有する生物群の個体別微量元素濃度分析法である。これは、高次生物で実施中の生物種別の元素恒常性評価を、低次生物に応用する基盤を整備するためである。微細藻類、原生生物、小型甲殻類などを対象に、放射光X線マイクロビームを用いた個体別微量元素濃度・形態分析法の開発状況と展望について説明する。
(3) 環境 〜21世紀の陸水学〜
湖沼は、小規模な調査グループで水・生物・堆積物の包括調査を完遂でき、一研究者のライフスパンで環境変動への自然応答を観測できる貴重な天然の実験場である。湖沼学は長い歴史を有し、比較湖沼学的視点には目新しさがないが、そのような視野が共有されていた時代と比較すると、微量元素安定同位体分析や環境DNAなど、新しい技術ツール開発も進んできた。研究例として、(i)琵琶湖のヒ素濃度の経年変化、(ii)DOC生成による大気中水銀のポンプ機構、(iii)深水層酸素消費への底質由来還元型分子の寄与、(iv)湖沼の微量元素ホメオスタシス、の概要を紹介する。
—– 2021年度 GBSセミナー予定 —–
第1回 4/26(月) 板井
第2回 5/24(月) 佐々木
第3回 6/21(月) 博士中間発表
第4回 9/21(火) 修士中間発表
第5回 10/25(月) 鍵
日時:2021年2月2日(火)17:00-
演題:海洋生物の絶滅を誘発した三畳紀の「雨の時代」~カーニアン多雨事象とパンサラサ海の巨大火成岩岩石区~
講演者:尾上哲治(九州大学)
要旨: 中生代の三畳紀(約2億5190万年前~2億130万年前)という時代の気候は、総じて高温乾燥であったことが知られています。ところが、三畳紀の「カーニアン階」と呼ばれる時代の地層には、世界各地で湿潤な気候の痕跡が認められており、それらの記録は、当時の地球に約200万年間にわたる「雨の時代」が存在したことを示していました。「カーニアン多雨事象(CPE: Carnian Pluvial Episode)」と呼ばれるこの気候変化は、いくつかの生物群の絶滅や大規模な進化的変化があった時期と一致していることが知られています。そして最近では、この長雨を引き起こした原因として、現在の北米北西部に分布するランゲリア洪水玄武岩の火山活動が挙げられてきました。しかし玄武岩の噴出年代測定に伴う不確定性のために、ランゲリアの火山噴火とカーニアンの気候変化及び生物群の変化が同時期に起きたと明言するのは難しいとされてきました。 そこで私たちの研究グループは、カーニアン多雨事象と火山活動の関連性について解明するため、岐阜県坂祝町の木曽川河床に観察されるチャートという岩石を対象にオスミウム同位体分析を行いました。研究の結果、地球内部のマントル物質に特有の低いオスミウム同位体比が、カーニアン前期のチャートから検出されました。これは、大規模な火山活動に由来するオスミウムが、カーニアン前期の海洋に大量に供給されたことを意味します。この火山活動により噴出した火山岩の候補としては、上記のランゲリア洪水玄武岩が挙げられますが、日本の三宝帯や極東ロシアのタウハ帯といった地質体にもカーニアン前期に噴出した玄武岩が総延長3000 kmにわたって分布しています。本発表では、これらの環太平洋を取り囲むように分布する玄武岩は、カーニアン前期の超海洋パンサラサ海で巨大火成岩岩石区を形成していたとする仮説を提唱し、カーニアン多雨事象がこの大規模火山活動により引き起こされた可能性について議論します。
日時:2020年12月21日(月)18:00-
演題:「福島原発事故により放出された放射性セシウム含有微粒子の内部構造と物理化学的性質」
講演者:奥村大河
要旨:2011年3月に発生した福島原発事故によって大量の放射性物質が環境中に放出され、周辺地域に汚染が広がった。ガスとして放出されたと考えられる放射性セシウムは雨滴とともに地上へ落下し、主に層状珪酸塩等の土壌中の鉱物に収着されたと考えられている。これとは別に、放射性セシウムを含有した珪酸塩ガラス微粒子CsMP(radiocesium-bearing microparticle)が損傷した原子炉内で生成され、環境中へ放出された。CsMPは概して数ミクロン以下の球形を呈し、上記の放射性セシウムを収着した鉱物に比べて単位体積当たりの放射能が非常に高い。またサイズが小さく大気中を浮遊しやすいため、関東を含め広範囲に運ばれ沈着した。発表者らの研究グループでは、CsMPの組成や内部構造に加え、その環境動態に関連する熱特性や溶解特性等の物理化学的性質を調べてきた。さらに最近では、放射性セシウムを収着した鉱物粒子とCsMPの酸性溶液中での溶解特性の違いを利用し、CsMPの存在量を見積もる手法を提案した。本発表では、これまでに得られたCsMPに関する知見を紹介する。
日時:2020年11月30日(月)18:00-
演題:「中赤外レーザー分光法を用いたCO2同位体種測定の展開」
講演者:狩野彰宏(地球生命圏科学講座)
要旨:
炭酸塩鉱物の同位体組成は古気候や物質循環の理解に大きく貢献してきたが,近年,炭酸凝集同位体 (47CO2) に代表されるように,炭酸塩-CO2のアイソトポログを用いたプロキシ開発が進展しつある。CO2のアイソトポログの測定は原理的に従来型の質量分析計ではできないが,アイソトポログの特性吸収線を読み取る赤外線レーザー分光計では可能である。より少量の試料で,あるいはより正確な測定結果を得るために,分析方法とともにハード面での開発も進みつつある。現時点では12C17O16Oと13C18O16Oについての測定が可能になり,数年以内に13C17O16O(存在度1.5ppm)の測定も可能になるだろう(Double clumped)。
セミナーでは,この方法により進展が見込まれる17O異常(12C17O16Oの存在度異常)についても解説する。陸成炭酸塩の17O異常は水蒸気発生時の湿度情報を保存していると思われ,石筍,土壌炭酸塩,蒸発成炭酸塩に応用できるだろう。また,陸棲脊椎動物の歯エナメル炭酸塩は大気酸素の低い17O異常を受け継ぎ,過去の動物の代謝様式の推定に使えるかもしれない。
日時:2020年10月26日(月)18:00-
演題:哺乳類系統における横隔膜の進化的起源
講演者:平沢達矢
要旨:
横隔膜は、胸腔と腹腔を仕切るシート状の骨格筋であり、呼吸の際に胸腔の容積を広げ肺に空気を取り込ませる機能を持つ。化石を手がかりにすると、横隔膜はペルム紀末(大気酸素レベルが急激に低下した時代)に哺乳類系統で進化したと推定されるが、哺乳類以外の脊椎動物では横隔膜と比較しうる構造がなく、どのように進化してきたのか、これまでまったくの謎であった。この問題に対し、胚発生における横隔膜の筋前駆細胞が特有の遺伝子発現を持ち分化が抑えられた状態で長距離移動する「移動性筋前駆細胞(MMP)」というタイプであることに注目、骨格形態と胚におけるMMPの分布の関係性から祖先動物におけるMMP分布を復元することで、横隔膜は前肢筋、特に肩甲下筋が重複することで成立した可能性が高いことが分かった。この進化は脊椎動物胚発生で頭尾軸方向の位置情報を司るHox遺伝子の発現パターンと関連していると予想され、本セミナーではそれに関する進行中の実験についても紹介する。
地球生命圏講座 修士中間発表会
日時:2020年9月24日(月)9:00-17:15
Zoom開催:URLは前日に回覧します
9:00 – 9:30 山口 智弘
「二枚貝類Anadara属の貝殻形態における定量的解析」
9:30 – 10:00 水上 綾乃
「脊椎動物の陸上進出に伴う眼構造の進化」
10:00 – 10:30 長谷川 菜々子
「鉄安定同位体比アイソスケープを用いた沿岸性・外洋性海棲哺乳類の生態解析と生物地球化学的物質循環研究への応用」
(休憩)
10:40-11:10 長澤 真
「日本におけるレアアースイオン吸着型鉱床の探査とその地球化学的研究 」
11:10-11:20 中路 渚
「腹足類のDNAバーコーディングと環境DNAを用いた多様性の検出」
11:20-12:10 中里 雅樹
「ICP飛行時間型質量分析計を用いたナノサイズの鉱物微粒子の元素組成分析」
(昼食)
13:00-13:30 中川 賢人
「ヨーロッパモノアラガイの巻き方向と中枢神経系の関連」
13:30-14:00 寺西 毅洋
「エアロゾル中のカドミウムの発生過程と環境中での挙動に関する考察」
14:00-14:30 田村 一紗
「放射光X線マイクロビームを用いたナノ・ピコプランクトンの個体別元素分析法の開発」
14:30-15:00 多田 誠之郎
「鼻腔構造にもとづく恐竜類における内温性獲得過程の解明」
(休憩)
15:15-15:45 高宮 日南子
「金属硫化物チムニー内部の極小古細菌の生態の解明」
15:45-16:15 末岡 優里
「火星の岩石内生命の理解に向けたアナログ試料の分析技術の開発:海洋地殻上部の玄武岩質溶岩の研究例」
16:15-16:45 市東 力
「中性子回折を用いたguyanaiteの結晶構造解析と水素の挙動に見られる温度・圧力依存性」
16:45-17:15 太田 成昭
「シグナル伝達因子を用いた巻貝の貝殻成長メカニズムの解明」
発表時間は1名あたり20分、質疑応答10分です。
東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 地球生命圏科学講座