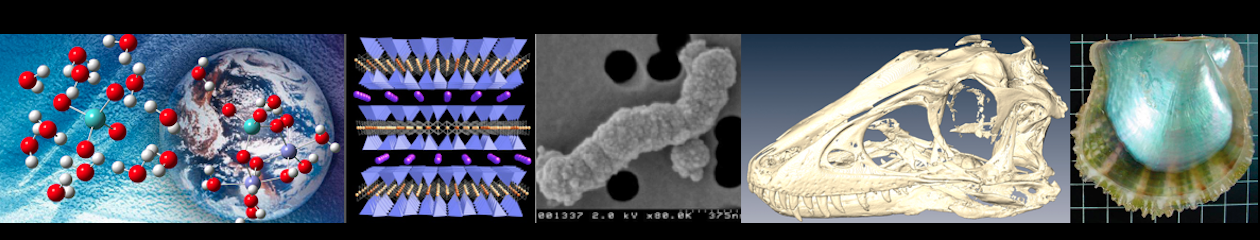講演者:小暮敏博 教授
場所:理学部1号館336号室
演題:原発汚染土壌の研究を振り返る
要旨:
2011年3月11日の東日本大震災は阪神淡路大震災とともに戦後最大の自然災害となり、それによって引き起こされた福島原発事故は放射能による未曾有な環境汚染をもたらした。原発から周囲に飛散沈着した放射性セシウム(RCs)がどのような状態で環境中に存在するかは、今後の汚染の推移と効率的な除染法を考えるための最も基本的な情報であり、小暮研究室ではこの11年間、福島汚染土壌中のRCsの存在形態などを明らかにする研究を続けてきた。その中で、土壌中でRCsを吸着固定している鉱物種とそこからの脱離特性、さらに破損した原子炉から直接飛散したRCs含有放射性微粒子の本質とその諸性質などを報告した。そこでは粘土鉱物のこれまでの研究の蓄積と電顕による微小領域の分析技術が活用されてきた。本発表ではこれまでの研究の経緯を振り返り、今後さらに明らかにすべき問題について考える。
講演者:白井厚太朗 准教授
場所:理学部1号館336号室
演題:地球生命圏を同位体で科学(化学)する
要旨:
気候変動は生物地球化学的物質循環を介して生態系に影響を与え,それらの相互作用や共進化史は地球科学における重要な問いである.生物硬組織は化石として保存され,その化学・同位体組成から環境や生態履歴の情報を引き出すことが可能である.環境・生態系の共進化史のさらなる理解のためには,古環境復元の高解像度化・多項目化のみならず,気候変動に対する生態・生態系の応答を復元する新たな指標の開発が必要である.
今回は生命圏に着任後初めてのGBSセミナーなので,前半では自己紹介も兼ねてこれまでの古環境復元手法の開発や魚類回遊生態に関する研究を紹介します.後半では現在取り組んでいる化石試料を使った古環境復元や,海洋生物の新たな移動・回遊指標の開発について紹介します.
日時:2022年11月28日(月) 17:30~18:30(発表45分,質疑15分)
講演者:荻原成騎 助教
場所:理学部1号館336号室
演題:ハーキマーダイヤモンド(両錐水晶)の産状と形成過程
要旨:
米国ニューヨーク州ハーキマー郡とモホークリバーバレー周辺の苦灰岩から産出する無色から茶色の透明で18面の両錐水晶について、ハーキマーダイヤモンドという商品名が用いられている。ハーキマーダイヤモンドは、種々の包有物を持ち、条線がなく美しい照りが特徴である。その麗しい姿から、鉱物愛好家のみならず一般の人々にも非常に人気がある鉱物である。
ハーキマーダイヤモンドは、カンブリア紀後期の苦灰岩中に発達する。大型の結晶は、ストロマトライトの抜け殻(溶脱したストロマトライトの空隙)中に産出する。空隙内壁はグラファイトのコーティングがなされ、ハーキマーダイヤモンドはグイラファイトに載る産状で成長し、一部グラファイトを包有物として取り込んでいる。また、大型の結晶には茶水晶が混じる。
本発表では、NY州Herkimer郡Ace of Diamond鉱山とその周辺で行った野外調査の結果を中心に、ハーキマーダイヤモンドの形成過程について議論する。
日時:2022年10月24日(月) 17:30~18:30(発表45分,質疑15分)
講演者:砂村倫成 助教
場所:理学部1号館336号室+zoom
演題:深海海底面境界と微生物相
要旨:
境界層は物理化学条件の急激な変化に伴う生物の生育エネルギーが得やすい環境である。海底面は地球上で最大級の境界層であり、海洋から堆積物表層へは沈降粒子を通じて物質が輸送・貯蔵される。海底下から海洋へは、海底熱水やメタン湧水など密度差による流体の上昇、海溝や大陸棚では堆積物の深海への再懸濁を通じ、特定の環境でのフラックスが確認されている。一般的な深海では海底面上1000m程度から海底面に向けて微生物密度の上昇がしばしば観察され、深海海底面付近からの物質もしくは微生物バイオマスの供給が示唆されるが、海底面付近での海水-海底下の連続的な微生物群集の調査例は乏しく、その原因はわかっていない。本発表では、フィリピン海プレート上の8カ所の海山山麓で海底面を境界として堆積物から海底面高度100mまでの海水の連続的採取により微生物群集構造鉛直分布の調査結果を紹介し、海底面近辺での生物地球化学過程の多様性を議論する。
日程:2022年9月29日(木)
場所:理学部1号館336号室(zoomでのハイブリッド開催)
時間:下記プログラム参照
内容:GBS修士課程2年生による中間報告
発表時間等:発表20分・質疑10分
ハイブリッド開催ですが、報告者は原則対面での発表になります。
皆様のご参加と活発なご議論をお待ちしております。
・プログラム
10:00–10:30 田柳紗英「国内成層型湖沼のケイ素動態に関する地球化学的研究」
10:30–11:00 服部竜士「ストロンチウム等の多元素同位体比分析による白亜紀上位捕食者の生息環境・生態復元」
11:00–11:30 佐藤海生「環境DNAメタバーコーディング解析による津波堆積物識別手法の検討とイベント前後の生態系変遷の解明」
11:30–12:00 三木志緒乃「長寿二枚貝ビノスガイの貝殻成長線解析と酸素同位体比分析による高解像度気候変動復元」
― 昼休み ―
13:00–13:30 松本藍「ハシブトガラスの成長に伴う気嚢の発達様式」
13:30–14:00 吉村太郎「化学合成共生二枚貝のバイオミネラリゼーションによる硫黄解毒メカニズムと超深海における結晶安定化戦略」
14:00–14:30 廣田主樹「カイダコ類(アオイガイ科)の卵鞘でみられる生体硬組織の特徴とその進化」
14:30–15:00 松永尚樹「山林土壌を対象とした安価な代替放射能除染方法の検討」
― 15分休憩 ―
15:15-15:45 梅山遼太「脊椎動物の胸鰭の起源と初期進化」
15:45-16:15 渡邉拓巳「胚発生過程に着目した恐竜-鳥類系統における顎関節-中耳構造の形態進化」
16:15-16:45 今町海斗「船舶の排気ガスに含まれる硫酸エアロゾルが気候に与える影響について」
日程:6月20日(月)、22日(水)
時間:下記プログラム参照
内容:GBS博士課程2,3年生による中間報告
発表時間等:D3は発表35分・質疑15分,D2は発表20分・質疑10分
ハイブリッド開催ですが、報告者は原則対面での発表になります。
皆様のご参加と活発なご議論をお待ちしております。
————————————————–
2022年6月20日(月)
・会場:理学部1号館710号室 (Zoom併用)
・プログラム
9:00–9:30 D2多田誠之郎 「竜弓類における鼻腔に関連した吻部構造の形態進化」
9:30–10:00 D2吉澤和子 「魚竜形類の尾部軟組織復元と機能形態学的解析に基づく水棲適応史の解明」
― 30分休憩 ―
10:30–11:00 D2太田成昭 「貝殻成長におけるシグナル伝達因子Wntの役割」
11:00–11:30 D2末岡優里 「火星サンプルリターンを対象とした岩石内生命検出技術の開発」
11:30–12:00 D2中里雅樹 「コンドライト隕石中の超微粒子の同位体比分析法の開発」
― 昼休み ―
13:00–13:30 D2長澤真 「レアアースイオン吸着型鉱床の形成機構に関する地球化学的研究」
13:30–14:00 D2長谷川菜々子 「海洋生態系を通じた鉄循環に関する鉄安定同位体地球化学的アプローチ」
― 10分休憩 ―
14:10-15:00 D3名取幸花 「起源の異なるエアロゾルの分析による燃焼起源の指標としての金属元素同位体比の有効性の評価」
15:00-15:50 D3脇水徳之 「頭部神経系と頭骨吻部形態に着目した爬虫類の嘴構造の進化史と感覚機能の復元」
————————————————–
2022年6月22日(水)
・会場:理学部1号館101号室 (Zoom併用)
・プログラム
10:30-11:20 D3山口(福田)瑛子 「粘土鉱物への吸着反応の系統的理解に基づく金属イオンの環境動態解明」
11:20-12:10 D3蓬田匠 「先端X線分光法の開発によるウランの環境地球化学」
― 昼休み ―
13:00-13:50 D3石川弘樹 「現生鳥類の孵化後の成長に伴う骨学的形質の変化とその順序異時性」
13:50-14:40 D3佐藤英明 「軟体動物の貝殻形態および模様形成の数理的解析」
― 10分休憩 ―
14:50-15:40 D3髙橋玄 「魚類耳石における炭酸カルシウム結晶相の制御機構の解明」
15:40-16:30 D3中野晋作 「岩石内生命圏における微生物生態の解明」
日時:2022年5月30日(月) 18:00~19:00(発表45分,質疑15分)
講演者:高橋嘉夫 教授
場所:Zoom開催
演題:粘土鉱物中の鉄の酸化還元反応の地球惑星科学における多面的意義
要旨:
粘土鉱物(主にスメクタイト)など層状ケイ酸塩の主に8面体層中に含まれる鉄のFe(II)とFe(III)の変化は、Stucki et al. (1984)の最初の論文以降、依然として多くの研究がなされてきている。その理由は、その反応機構が未だに十分に解明されていないためである一方、粘土鉱物はあらゆる地球惑星科学・環境科学試料中に存在し、その影響が多岐に渡る可能性があるからである。我々は主に、XAFS法による検出を基盤にしながら、その酸化還元反応が様々な現象に与える影響について考察することを試みている。主に以下のトピックスについてお話ししたい(トピックスの順番は、扱う環境として酸化的環境から還元的環境の順番に並べた)。
(i) 土壌中の酸化還元反応における粘土鉱物中のFe(II)/Fe(III)比変化の占める位置づけと微生物活動への影響(M1・清水優希さん)
(ii) 粘土鉱物中のFe(II)/Fe(III)比変化が粘土鉱物の吸着容量に与える影響(PD・田中雅人さん;M1・田中啓資さん)
(iii) 地層中のウランの酸化還元状態に及ぼす層状ケイ酸塩の影響(2021年度修士修了・竹田早英桂さん)
(iv) 隕石・リュウグウ試料中の層状ケイ酸塩の鉄価数のEh計としての意義や非生物的有機物合成への関与(D1・河合敬宏さん)
今後は、これらの基盤となる層状ケイ酸塩中の鉄価数比とEhの関係(Gorski et al., 2013)を蛇紋石に対して求める研究を進めたいと考えている。
日時:2022年4月25日(月) 18:00~19:00(発表45分,質疑15分)
場所:理学部一号館336号室
講演者:遠藤一佳 教授
演題:動物ミトコンドリアDNAにおける新規遺伝子の進化(De novo gene evolution in animal mitochondrial DNA)
要旨:
遺伝子の進化プロセスは、遺伝子の塩基配列をもとに地球と生命の歴史の解明を図る上で重要であり、遺伝子の重複、使い回し、融合、欠失、水平伝播など様々な現象が知られている。その中で最も研究が遅れているのが、新規遺伝子の進化(誕生)である。それでも近年の高速シーケンサーによる近縁複数種のゲノム解読等により、新規遺伝子進化が、予想以上に頻繁に起きていることがわかってきた。ここでは、そのような新規遺伝子進化が、腕足動物シャミセンガイ類のミトコンドリアDNA(mtDNA)でも起きていることを発見したので紹介する。この新規遺伝子候補は、(1)共通祖先における不在、(2) 転写産物と翻訳産物の存在、(3) 近縁種間での配列の保存、(4)自然選択を経験という、新規遺伝子認定の規準を満たすほか、mtDNA上で新規に進化したことを示すいくつかの特徴を示す。ただし、この新規遺伝子がコードするタンパク質の正体については今後の研究が必要である。mtDNAでの新規遺伝子進化の報告はこれまでにない。mtDNAは核DNAに比べ、圧倒的にサイズが小さく扱いやすいため、今後新規遺伝子進化を研究する有用な実験系になる可能性がある。
日時:2022年2月4日(金) 17:00~18:00(発表45分,質疑15分)
講演者:加藤真悟 博士(理化学研究所バイオリソース研究センター)
演題:分子生態学と地球惑星科学の相互作用
要旨:
地球表層環境におけるエネルギー・物質循環の過去・現在・未来を議論する上で、微生物の存在を無視することはできない。しかしながら、地球上に存在する微生物の大部分は、まだ実験室内で培養できておらず、その機能や役割はほとんど未知である。それら機能未知の未培養微生物は、宇宙を満たす暗黒物質(ダークマター)になぞらえて、「微生物ダークマター」と呼ばれている。近年、対象となる微生物を培養できなくても、環境中のその微生物由来の生体分子(主に核酸)を分析することができるようになった。分子(微生物)生態学は、それらの生体分子を対象にして微生物の生態に迫る学問分野であり、「微生物ダークマター」の全貌解明において中心的な役割を担っている。演者は、これまで海底熱水噴出域や温泉といった極限環境に生息する「微生物ダークマター」を対象として、培養を基軸にしつつ、分子生態学なアプローチも進めてきた。本セミナーでは、演者のこれまでの研究成果を紹介しつつ、分子生態学の歴史を振り返り、現状を把握し、今後の分子生態学と地球惑星科学の相互作用について皆さんと一緒に考えてみたい。
日時:2021年12月20日(月) 18:00~19:00(発表45分,質疑15分)
講演者:鈴木庸平 准教授
演題:生命-岩石相互作用研究の最前線
要旨:
生命の誕生には岩石と水の反応で生成する還元物質や、核酸、タンパク質、脂質等の生体分子の役割を果たすとされる粘土や金属硫化物が重要視される。深海や地底の岩石内生命圏は光合成産物から隔離される場合、光合成生物誕生前の初期地球生態系と類似すると考えられる。そのような岩石内部で、どのようにエネルギーを獲得し、生命活動を営んでいるか不明であった。しかし、試料採取技術、ゲノム解読技術、局所分析技術の近年の発達により、始原的な生命が発見され、生命の誕生で重要視される物質との関連性が明らかになりつつある。本セミナーでは、地球外からの発見も期待される岩石内生命について、地球初期から存在する岩石との相互作用について最新の科学成果を紹介する。
東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 地球生命圏科学講座